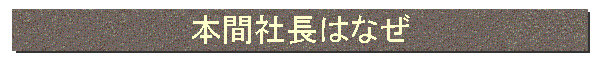
新生日債銀の本間忠世社長は、なぜ、自殺をはかったのでしょうか。
本間氏は日債銀の倒産には、―切関わっていませんでした。総会屋への利益供与事件をきっかけに第一勧銀でも宮崎元会長が自殺をするという痛ましい事件もありましたが、本間氏は元日銀理事であり、日債銀OBでもありません。つまり銀行の経営破たんそのものにはいっさい関わっていないのです。
つまり日債銀が再建できるかどうについての責任こそ問われるものの、日債銀が行ってきた不良債権隠しの露見を心配する必要もなかったし、法令違反で刑事罰をうIナる恐れも一切ありませんでした。
にもかかわらず、なぜ本間社長は、民営化の再スタートを切った矢先に、みずからの命をたたなけれぱならなかったのでしょうか。
日本人選手の華々しい活躍にわくシドニ―五輪報道のかげで、本間社長自殺に関する報道はきわめて少ないものでした。全国紙を見渡しても、毎日新間だIナが、自殺が発覚した翌日(9月22日)にカンタンな特集を組んだ程度でした。
その毎日新間によれぱ「本間社長の遺書は5通」残されていたていたいそうです。
「本間社長の遺書は5通残されていた。家族のほか、出身母体である日銀の現・前総裁らにあてたものもあった。捜査に当たった大阪府警は中身を確認しようとしたが、関係者は一部を除いて拒否したという。本間氏は社長就任後、体調がすぐれなかったようで、近親者には『日債銀の社長になることは本意ではなかった』という趣旨の発言をもらしていたという」(毎日新間9月22日付朝刊3面)
そして毎日新間はこんな小見出しをつIナました。「重責が重荷に?」だが、いきなりそう言われても、ピンとこないでしょう。重責? 当然でしょう。血税3兆円をつぎ込んだ国営銀行を引き継ぐうえに、旧日債銀の中身がぼろぼろであることは金融関係者なら誰でも知っていることなのですから、その再建がいかに難しいか。日銀出身の本間氏は誰よりもわかっていたはずです。すべてをわかったうえで、火中の栗を拾った本間氏だったのに、なぜ、新生日債銀発足からわずか半月後に、みずからの命を絶たなけれぱならなかったのでしょうか。
もちろん今となっては真相は永遠に謎ですが、本間氏周辺から間こえてくる客観情勢を整理していくと、わずかぱかりとはいえ、本間氏の心中を垣間見ることができます。
●社長の椅子は本間氏にとって針のむしろだった
本間氏は一九六三年に東大を卒業して日銀に入行しました。九〇年には金融システムの安定をになう信用機構局が日銀内に創設されたのを機に、初代信用機構局長に就任。北海道拓殖銀行が破綻し、山―証券が自主廃業に追い込まれた九七年には信用機構局担当理事として陣頭指揮をとった人物です。
信用秩序の維持という大目的のために作られた信用機構局の初代局長であるにもかかわらず、担当理事としてやったことは金融機関を破綻させることぱかりであったために「ミスター破綻」などと揶揄されたこともありました。
しかし拓銀、山―破綻の五ヶ月月前の一九九七年六月には、ある金融機関の経営不振に際して、まったく異なる行動をとっていました。じつはそれが日債銀だったのです。大蔵、日銀連合は、日債銀の経営破たんが目に見えてきたときに、当局主導で三十四の金融機関に対して「奉加帳増資」を強制しました。日債銀が新たに発行した、二千九百億円分の株式を民間銀行に対して、体力に応じて、半ぱ強制的に買わせたのです。
ところが旧日債銀はその後破たんし、民間銀行が買った二千九百億円分の株式は、文字通りの"紙くず"となりました。民間銀行にしてみれぱ、まったくもって騙されたというほかありません。それがいまだに大きなしこりとして残っていますが、この奉加帳増資を仕切った張本人が日銀理事時代の本間氏であったわけです。
その本間氏が、新生日債銀の社長を快諾するわけがありません。旧日債銀の頭取ポストは日銀OBにとっては貴重な天下りポストでしたから、―時国有化されたとはいえ、日銀としては何が何でも死守したいポストだったのです。ところが、火ダルマの日債銀に飛び込むだけの覚悟をもった日銀OBなどいるはずがありません。御殿女中などと揶揄されてきたひ弱な日銀エリ―トたちは、誰―人として、火中の栗を拾い上げようとしなかったのです。
そして、最後の最後に、お鉢が回ってきたのが、奉加帳増資で民間銀行から恨みをかっている本間氏だったというわけです。
真偽のほどは定かではありませんが、次期日銀総裁の呼び声も高い「福井前副総裁の、たっての頼みを本間氏は断れなかった」という日銀関係者は少なくありません。
本間氏は日債銀のリスタ―トに際して、新銀行はべンチャ―企業への融資やインタ―ネット金融を事業の柱にしつつ、大企業向けのブロジェクト融資にも積極的に取り組んでいくという方向性を明らかにしつつ、「ロ―リスク・ロ―リタ―ンの従来型銀行と、商工ロ―ンのようなハイリスク・ハイリタ―ンの中間に位置する銀行を目指したい」という将来像もえがいてみせました。
では、いつまでに新生日債銀を再建するのか? 記者たちの質問に本間社長はこう答えています。
「先行き三年ないし五年の間に証券市場に再上場できるように新銀行を立ち上げていきたい」
しかし力強い言葉とはうらはらに、本間氏の精神は重く沈んでいました。日債銀のなかみがぼろぼろであることを誰よりも知っていたのが本間氏です。そんな簡単に再建ができるわけがありません。そこにもってきて、そごうへの債権放棄問題をきっかけに'8月には日債銀の「暇症担保特約は破棄すべきだ」という声もあがり、国と取り交わした売買契約の見直しが国会で取り上げられるという事態まで発生。国民の立場から見たら、損したら国が買い取りますよという暇症担保特約は許しがたい背信行為とうつりますが、それを前提に不良債権をまるがかえで旧日債銀を買った側にしてみれぱ暇症担保特約はまさに「命綱」いがいの何ものでもありません。
そんなぎりぎりの状況にまで追いやられた上に、本間氏をささえるべきオーナー役員たちの人間関係は必ずしもうまくいっていませんでした。
オーナー株主とは、いわゆるソフトバンク連合の社長たちです。ソフトバンクの孫正義社長、オリックスの宮内義彦会長、そして東京海上の樋口公啓社長の三人です。
なかでも圧倒的な影響力をもっていたのは新生日債銀の48.88の株を持つソフトの孫さんでした。
孫さんがいい悪いということではなく、客観的な状況をだけをいいますが、新銀行の経営について孫―本間の二人は銀行発足前からかなり意見が対立していたようです。
こうした状況の中で本間氏は「自己崩壊してしまったのではないか」というのが、私が信頼する新間記者の感想であり、また私自身の理解なのです。
血税を三兆円もつぎこみながら、なぜ、もっとすっきりとしたカタチで日債銀の再建に取り組めなかったのか。かえすがえすも残念でなりません。
みずから命を絶った本間氏の弱さを私は憎みますが、彼はまぎれもない犠牲者です。
ご冥福を祈ります。
(財部誠― ハーベイロード)