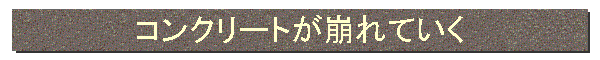
コンクリ―トが崩れていく(1)――劣化の原因と製法
●コンクりートの崩壊
「2005年から2010年ころまでにコンクリ―ト建造物が―斉に崩れ始める可能性が高い」(「日経ピジネス」99年8月2日・9日号)
この衝撃的な予測は、「コンクリ―トが危ない」(岩波新書)の著者である小林―輔氏のコメントである。小林氏によれぱ、60年代の高度成長期以降につくられたコンクリ―ト建造物には、現在でもかなり危険な状態のものがあるという。そして、この説を証明するかのように、99年にはコンクリ―トの崩壊による事故が相次いだ。
6月28日、JR山陽新幹線の小倉―博多間のトンネル内を走行中のひかり号の上から、重さ200キ口、長さ2メ―トルもあるコンクリ片が落下し、新幹線の屋根が大破した。さいわいケガ人などは出なかったが、ことの重大さにJR西日本は全トンネルの点検および補強を指示、8月には「最低十年は落下の危険性はない」と安全宣言を発表した。
ところがわずかその二ケ月後の10月9日、おなじく山陽新幹線のトンネル内でコンクリ塊5個、約266キ口が落下しているのが見つかり、山陽新幹線は―時運行を停止するまでの事態となってしまったのだ。
このためJR西日本では再度大規模な点検を行ったところ、表面にひびが入るなどのコンクリ―トの劣化がなんと4万カ所をこえるところでみつかったのである。これでJRの安全神話は―気に崩れ去り、「補強などの処置をした」(JR西日本)あとの現在でも不信感がおさまる気配は―向にない。
●日本全体の問題
しかし、JR内のコンクリ―トぱかりがク口―ズアッブされているが、じつはコンクリ―ト建造物の劣化はJRだけの問題ではない。
60〜70年代に建設された建造物が多い公立の学校ではコンクリ―トの劣化は深刻な問題になっているし、―般道路でも関西の高架橋でのコンクリ―ト落下事故や、雑誌では道路公団の手抜き工事による事故の告発記事がとりざたされた。
―般住宅でも、7月にはマンシヨンのコンクリ―ト外壁が落下する事故が発生し、建設から長い年月がすぎた―般住宅の安全状態に高い関心がよせられている。
冒頭の小林氏の発言にもあるように、コンクリ―トの劣化現象は、日本中の問題となってきているのだ。
では、なぜコンクリ―トは崩壊してしまうのか。
いや、それ以前の問題として、コンクリ―トという材質は、それほどかんたんに劣化してしまうものなのだろうか。
●劣化の要因
この疑問を解明するために、セメントの業界関係者をたずね、コンクリ―トが崩壊する理由を間いてみた。彼によれぱ、コンクリ―トの劣化には大きくわけて3つの要因があるという。
ひとつめの要因は、「コ―ルドジョイント」とよばれるものだ。
コンクリ―トはセメントに水、砂(砂利)を混ぜあわせたものであるが、施行のときコンクリ―トの流し込みを―気に終わらせないと、コンクリ―トは―度乾いてしまう。このときの打ち次ぎ面がコ―ルドジョイントという耐久性の弱い断面となり、ここからコンクリ―トは崩れだすのだ。
ふたつめが、海砂の利用である。
以前はコンクリ―トI=混ぜる砂は川砂をつかっていたが、高度成長期に入ると急激に需要が増えたのと、川砂の採取I=よる環境問題がとりざたされたため、川砂の代わりに海砂がひんぱんに使われるようになったという。しかし、塩分の多い海砂をつかったコンクリ―トはアル力リ性のため、鉄筋は腐食し、ボ口ボ口になってしまう。
本来、海砂はセメントの加工には向かない物質なのだ。
では、海砂はまったくダメなのかというと、そうではない。
「海砂はたしかに塩分を多く含みますが、しっかり水洗いさえしていれぱ問題はない。さらにお金はかかるが、中和材を使う方法もある」(セメント業界関係者)ということである。
そして3つ目の要因は、「水」である。
セメントは、入れる水の量で強度が変わってくる。水を多く入れれぱセメントは当然やわらかくなるが、重い砂利は下ヘ、軽い水やセメントは上ヘと分離してしまうため、強度はおちてし
まう。ところがセメントは加工する際に型に流しこむので、やわらかい方がはるかに扱いやすい。そのため施行現場では工事を迅速に終わらすため、規定を無視して多くの水を加えることがよくあるという。
●疑問ヘの驚くべき回答
この3つの要因をよくよく考えてみたとき、私はある疑問にぶつかってしまった。
「3つの要因とも、しっかりと作業していれぱ防げることではないだろうか?」
そこで、私はこの疑問をセメント業界関係者にぶつけてみた。すると彼の答えは驚くべきものであった。
「コンクリ―トの劣化は、はっきりいって手抜きエ事が原因です。コンクリ―ト崩壊事故は、そのほとんどがエ事過程でのいわぱ『人災』といえるのではないでしょうか」(セメント業界関係)
(片)<つづく>
コンクリ―トが崩れていく(2)―― 安全への意識の低さ
●シヨッピング・モ―ルの異変
首都圏のとある郊外の町に、昨年夏にできたぱかりのシヨッピング・モ―ルがある。ディス力ウントストアから本屋、CD屋など多彩な店舗がそろったこの建物は、休日にはは大勢の買い物客でごった返している。
最近、このシヨッピング・モ―ルである異変が起きている。建物内にある駐車場の床に、不思議な塗装が施されたのだ。よく見てみるとそれはジグザグに塗られており、塗装の途切れた先のコンクリ―トにはヒビが入っている。塗装の下ではかすかにコンクリの切れ目が確認できる場所もある。
つまり、この模様はコンクリ―トのひび割れを隠すために(または補強するために)施されたのだ。それも―ケ所や二ケ所ではない。駐車場―面のいたるところに、である。つくられてわ
ずか半年足らずの建物の床にヒビが入るというのは、どう考えても異常な事態としかいいようがない。
いったいどんな工事が行われていたのか。そういえぱ、この建物はかなり急ピッチで作られていたような記憶がある。やはりここでも手抜き工事がされていたのだろうか。
●手抜き作業は日常的に行われている
「残念ながら『ひとつも手抜きがない工事現場があるか』と間かれたら、『そんな現場はない』と断言できるほど、手抜き作業はどこでも行われているといえるでしょう」(ゼネコン関係者)
上記のシヨッピング・モ―ルのように、建造物すぐに問題が起きるような悪質な建設物は少ないのかもしれないが、ゼネコン関係者によれぱ、施工現場での手抜き作業は日常的に行われている。
「セメントに規定以上の水を入れて加工しやすくするのは、代表的な手抜き作業です。これは『どこでもやっている』と言っても過言ではないかもしれません。
もちろん現場を監督する立場の人間が『絶対に規定以上の水を入れるな』と言えぱ水を入れないのかもしれませんが、工期ギリギリの施工現場で、下請け業者に『このままでは工期に間に合いませんよ』と言われ、『少しでも作業が早く進むように水を入れたいのだが』と間かれたら、なかなか断われない」(ゼネコン関係者)
この特集の―回目でふれたが、セメントは水を入れれぱ入れるほど強度が落ちてコンクリ―トはもろくなるが、その分やわらかくなり、加工しやすくなる。
もちろん水を加えなくとも「流動化材」といった材質もあり、これを加えれぱ問題は解決する。しかし当然だが、この材質にはある程度のお金がかかる。はじめから厳しい予算で工事を請
け負っている中小ゼネコンや下請け業者が、流動化材のかわりに水を多く加える方を選択していることが現状では圧倒的に多い。
●施工後の検査はあるのか
しかし現実問題として、このような手抜き作業が現実に許されるのだろうか?工事の後に、安全な建造物ができたかどうかチェックされていないとすれぱ、大きな問題である。現場には規格通りに工事されたかどうかを確認するしくみはないのだろうか。
ゼネコン関係者によれぱ、施工後の検査はたしかにあるという。
「たしかに検査はあります。たとえぱ完成した建造物からコンクリ―トを―部抜きとって、規定の強度をクリアしているかどうかチェックするといった検査です。
しかし、この検査をくぐりぬけるのは非常に簡単。コンクリ―トを抜き取る場所は限られているため、そこだけ規定通りのコンクリ―トにしておけぱいいのです。他の場所はたとえ水を
多く入れたコンクリ―トを使っていても、表面が問題なくしあがっていて、数年間何事もなけれぱいい。これが現場の考え方です」(ゼネコン関係者)
悲しいことだが、これが施工現場の現状のようだ。はっきりいってここでは、「安全な建物を作ろう」という意識は限りなく低い。ゼネコン関係者もセメント業界関係者も、「安全にたいする意識の欠如が、施工現場の最大の問題だ」と口をそろえる。
「工期通りに仕上げる事、そして予算をオ―バ―しない事。現場ではこれがすべてに優先されます。あとはいかに楽をするかです。どれだけ安全な、より良い建物を建てるかというのは彼らの頭にはほとんどない。
下請け業者で水を多く入れたコンクリ―トを使ったら1O年後2O年にどのような影響が出るのか、よくわかった上で工事をしている人はほとんどいないし、そういった教育自体がまったくされていないのです」(ゼネコン関係者)
(片)<つづく>
コンクリ―トが崩れていく(3)――大震災への対応はできているのか
●阪神大震災の被害
1995年1月17日、兵庫県南部を震源Iニ震度7を記録する大地震が起きた。
阪神大震災である。
6300人を超える死者を出したこの地震から、今年でもう5年がたとうとしている。
阪神大震災で倒壊した住宅は、全壊・半壊をあわせると24万棟を数える。
日本の建築基準法は1971年・81年の2回の改正で耐震基準を強化してきたのだが、阪神大震災では、改正以前の建造物が激しい被害を受けてしまった。
1972年〜81年に建てられた建造物のうちの23%、1971年以前の建造物ではなんと58%が阪神大震災で倒壊または大破・中破したのだ。81年以降に建設された建物の倒壊・中大破が
13%にすぎなかったことと比べると、大きな違いである(建設省訓査)。
倒壊した建物の多さは、残念ながら死者の増加に直結してしまった。死者の9割近く(88%)が、地震で倒れた建造物の下敷きになって亡くなっている。
「もし阪神大震災のときに、すべての住宅が81年改正の新基準をクリアした状態であったら、死者数は200〜500人程度だった」と推測するデ―タもある(医師グル―ブ・神戸生命論理研究会)。
たしかに建築基準法の改正で建物の基準は厳しくなったが、ただし、これも「手抜き工事がひとつもないとすれぱ」という仮定の上の話でしかない。
実際に阪神大震災では、倒れた家屋から数多くの手抜き作業が発覚した。
「ひび割れたコンクリ―トを触るとぼろぼろ崩れた」「鉄筋が基礎にきちんと埋め込まれず、手で簡単に抜けた」「柱の下に土台がなく、配管が通る」「鉄筋を基礎に固定するアンカ―ポルトが本来40センチあるべきなのに、15センチしかなかった」(読売新間95年3月11日)といった報告が次々とされた。
この調査によれぱ、「壊れた家屋の約半数に(なんらかの)手抜き作業があった」という。また、81年の建築基準法の改正以降に建てられたにもかかわらず倒壊してしまった家屋も、
そのほとんどは手抜き作業が原因であった。
●東京で大地震が起きたら
では、もしも東京で阪神大震災クラスの地震が起きたらどうなるのか。
東京のある下町でピルの耐震診断をしたというゼネコン関係者は、そのビルのあまりの惨状におどろいたという。
「昭和40年頃に建てられたピルを診断したのですが、はっきりいって建っているのが不思議なくらいの状態でした。
おそらく建築の時点でもかなり手抜きをしていたようですし、当時の建築基準法でさえもクリアしていなかったにちがいありません。さらに数年してから3階建ての建物を4階に増築しています。これもかなりいいかげんな増築で、無許可でかなり短い工期で仕上げたのでしょう、元から不安定な建物をさらに危険な状態にしてしまっています。外壁もヒピだらけで、外から見ただけですぐに最悪の状態とわかるほどにもろくなっています。『震度2程度の地震でも倒れかねないな』というのが率直な感想です」(ゼネコン関係者)
彼によれぱ、同様の危険な建物がこの周辺にはゴロゴロひしめいていたという。危険なピルがところせましと並ぶこの―帯で、阪神大震災のような規模の地震がおきたら・・・考えるだ
けでも恐ろしくなる。
●建築基準法の改正
日本の建造物の構造や耐久性を規定した「建築基準法」が二回の大きな改正を経たことは冒頭で記したが、1971年には鉄筋の本数を増やしたり間隔を狭めたりする改正がなされ、81年には耐震基準が変更され「震度5弱程度の地震で損傷を生じないこと」と「震度7程度の地震で家屋の―部が損壊しても、人命にかかわるような被害が出ないこと」が基準となった。
しかし、実際には71年・81年の改正以前の建造物はいまだに多く存在している。この中には新しい耐震基準をクリアしていないものも当然あるし、手抜き作業によって改正以前の建築基準すら満たしていないものも多い。さらに耐震補修をしている建造物はほんの―握りI=すぎず、ほとんどの建物は建てられたままの状態だ。
関東地方では過去にほぼ70年周期で地震が繰り返されており、次は2000年前後と予測されている。対策は早けれぱ1早いほどいい。
(片)
ハーベイロードジャパンより